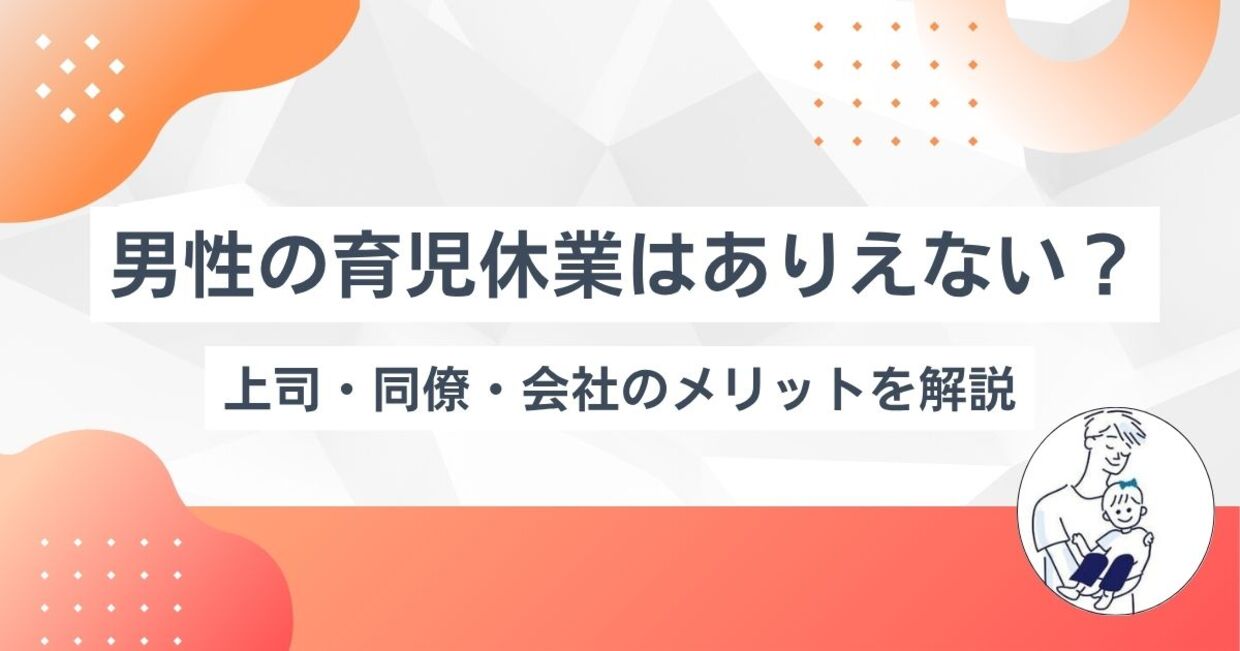どうも!「らんパパうーた」です。
6か月間の育児休業(育休)取得経験をもとにパパ、ママに役立つ情報をブログで発信しています!

「男性 育休 ありえない」って検索ワード、たまに見かけるんだけど、やっぱり、そう思ってる人もいるってことだよね。

うん、そう考えている人も、少なからずいると思うよ。

そうだよねー。
たしか「らんパパうーた」は、育児休業を2回取ったんだよね?そういう意見を見たとき、どう思う?

まだまだ新しい制度だから、否定的な意見があることが自然なことだと思うよ。
でも実は、上司や同僚、会社にとっても、男性の育児休業にはメリットがあると考えているよ。
この記事では、男性の育児休業が上司・同僚・会社にとってもメリットがある理由を解説します。
- 0歳と3歳のパパ
- 合計6か月間、育児休業を取得
- ランニングがライフワーク

男性の育児休業は、少子化に歯止めをかける一歩になる
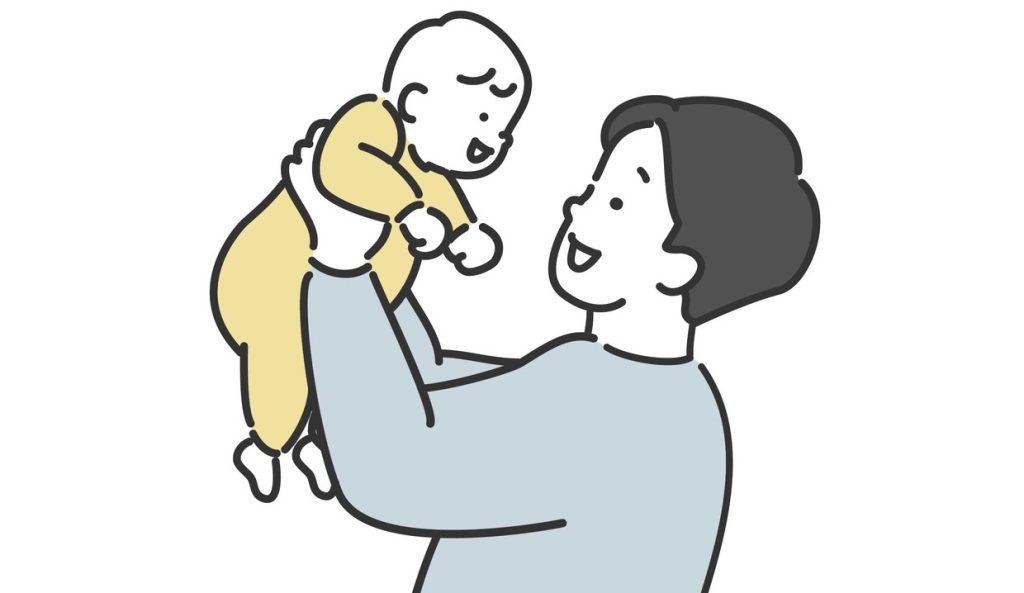
日本では、女性の社会進出が進む一方で、子育てや家事の負担が女性に偏っている現状があります。
その結果、仕事と育児の両立が難しく、第二子以降の出産をためらう夫婦が少なくありません。
産後2週間から1か月が「産後うつ」のピーク
特に出産後2週間から1か月は、ホルモンバランスや心身の変化からくる「産後うつ」のピークとも言われています。
この時期にパパが積極的に家事・育児に関わることが、ママの心身の回復と、育児の継続意欲に大きく関係します。
パパが家事育児に参加することで、第二子以降の出生割合が増える
実際に、パパが家事や育児に積極的に関わる家庭では、第二子以降の出生割合が高まる傾向がある調査結果も出ています。
これは、「子育てを夫婦で一緒にやれる」という安心感が、将来の家族計画に前向きな影響を与えていることを意味しています。
つまり、男性の育児休業取得は、家族の絆を深めるだけでなく、日本全体の少子化に歯止めをかけるための大切な一歩とも言えるのです。
上司にとって:部下の育児休業にメリットがある理由

このご時世、あまり大きな声では言えないけど、正直なところ、部下が育児休業を取ると、仕事が回らないし、手放しでは喜べないと思っていませんか?
ですが実は、部下の育児休業取得は、上司である皆さんにとってもプラスになることがあります。
上司自身の「休業」がスムーズになる
親の介護や自身の病気など、ライフイベントで休業を余儀なくされる可能性は誰にでもあり得ます。
そんなとき、育児休業を経験した部下がいれば、「休むのはお互いさま」という意識が職場に根づき、上司自身もスムーズに休業を取りやすくなります。
業務の属人化を見直し、仕事の平準化を行うチャンスになる
育児休業で一時的に人が抜けると、「あの人しかできない仕事」が可視化されます。
それにより、業務の棚卸し・マニュアル化・業務改善が進み、仕事の平準化につながります。
結果として、チームを改善・育成できる上司としての評価も高まる可能性があります。
育児休業は事前に計画が立てられるため、業務への影響を最小限にできる
育児休業は、介護や病気などによる休業と異なり、数か月前から発生することを把握できます。そのため、計画的な引継ぎが可能です。
退職の方が休業よりはるかに大きな損失になる
育児休業を希望する20代〜30代は、会社にとって貴重な戦力です。
上司の理解がないことで退職されると、数か月の育児休業よりはるかに大きな損失につながりかねません。
同僚にとって:一時的な負担より「チームの底力」アップ

育児休業で業務の一部をカバーすることになれば、「大変だ」と感じる同僚も少なくありません。
しかし、それでもなお、長期的に見ればチーム全体にとってプラスになる要素も多くあります。
自分も育児休業を取りやすくなる
前例があることで、自分が結婚・出産したときにも育児休業を取得しやすい環境が整います。
制度はあっても、実際に取得者がいなければ、使いにくいのが現実です。その壁を崩すのが同僚の育児休業です。
成長と評価のチャンスになる
育児休業者の業務を一部引き継ぐことは、自分のスキルの幅を広げるチャンスでもあります。
マニュアル化された業務であればなおさら、スムーズに担当でき、評価や信頼アップにもつながります。
会社にとって:離職防止・採用強化・企業価値アップ
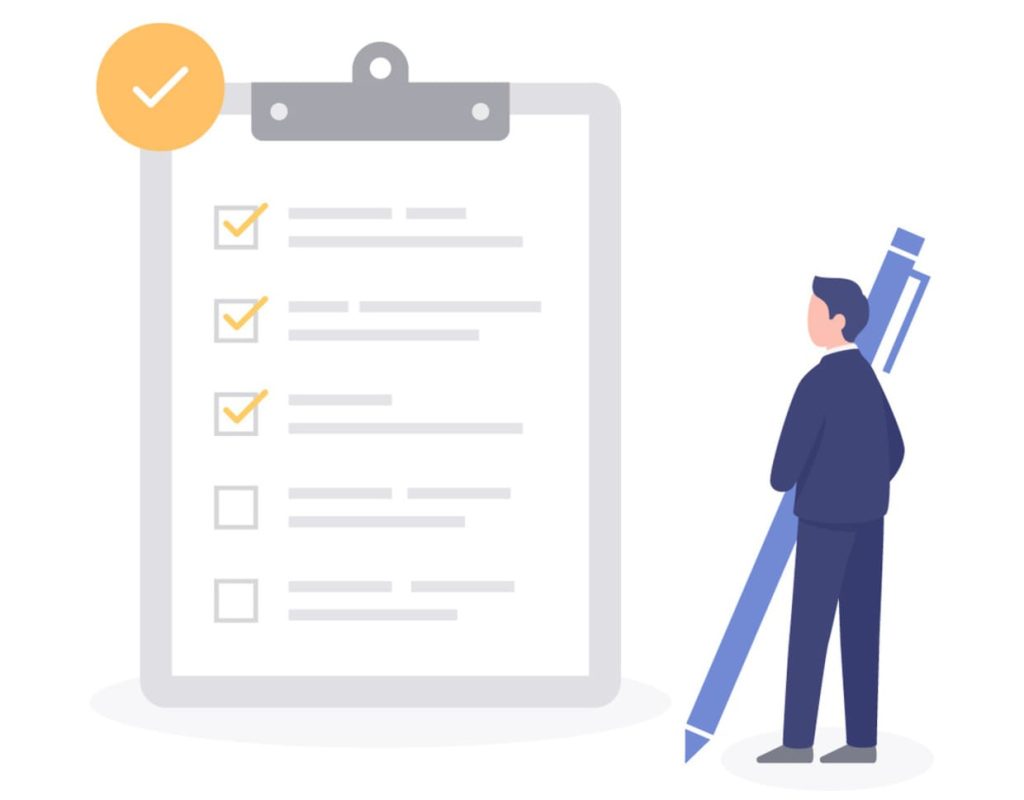
会社が男性の育児休業を推進することは、会社にとっても、大きなメリットがあります。
優秀な人材の採用と定着につながる
男性が育児休業が取りやすい職場であることは、就職・転職市場でのアピールポイントになり得ます。
東洋経済オンライン 5位は博報堂、4位はANA、ではトップ3は?2万人の学生が投票した「就職人気ランキング」をによると、育児休業を推進している伊藤忠商事が6年連続で1位になっています。
育児休業を推進しているから「就職人気ランキング」で1位であるとは言えませんが、ワークライフバランスを重視する若手世代にとって、大きな魅力につながります。
イノベーションのきっかけになる
育児というまったく違う環境での経験は、視野の広がりや新たな発想を生み出すきっかけになります。
異なる視点を持った人材が戻ってくることは、企業にとっても大きな価値です。
社会貢献としての企業価値向上
育児休業の取得が進むことで、少子化対策への貢献にもつながります。
投資家からの評価や、サステナビリティの観点からもプラスの評価を得やすくなります。
【まとめ】男性の育児休業は会社・上司・同僚にもメリットがある

男性の育児休業取得は、家庭だけでなく、職場や社会全体にとっても多くのメリットがあります。
- 少子化対策としての社会的意義
パパの育児参加が、ママの心身の回復を助け、第二子以降の出生意欲にもつながります。 - 上司にとってのメリット
部下の育児休業を通じて業務の属人化を解消し、チーム力を高めるきっかけになります。さらに、将来自分が休む立場になったときの下地作りにもなります。 - 同僚にとってのメリット
一時的な負担はあっても、育児休業取得のしやすさやスキルアップの機会につながります。 - 企業にとってのメリット
離職防止・採用力強化・企業イメージ向上・イノベーション促進など、長期的に見て大きなリターンがあります。
「らんパパうーた」自身、育児休業を3か月取得したことで、家族との絆が深まり、仕事への向き合い方にもポジティブな変化がありました。
育児休業を3か月取得して感じた本音や、自分自身の働き方の変化については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
育児休業は、みんなにとってプラスになる制度です。
これから育児休業を検討しているパパも、職場で部下・同僚の育児休業に向き合う方も、ぜひ前向きに考えてほしいと思います。
以上、「らんパパうーた」でした。