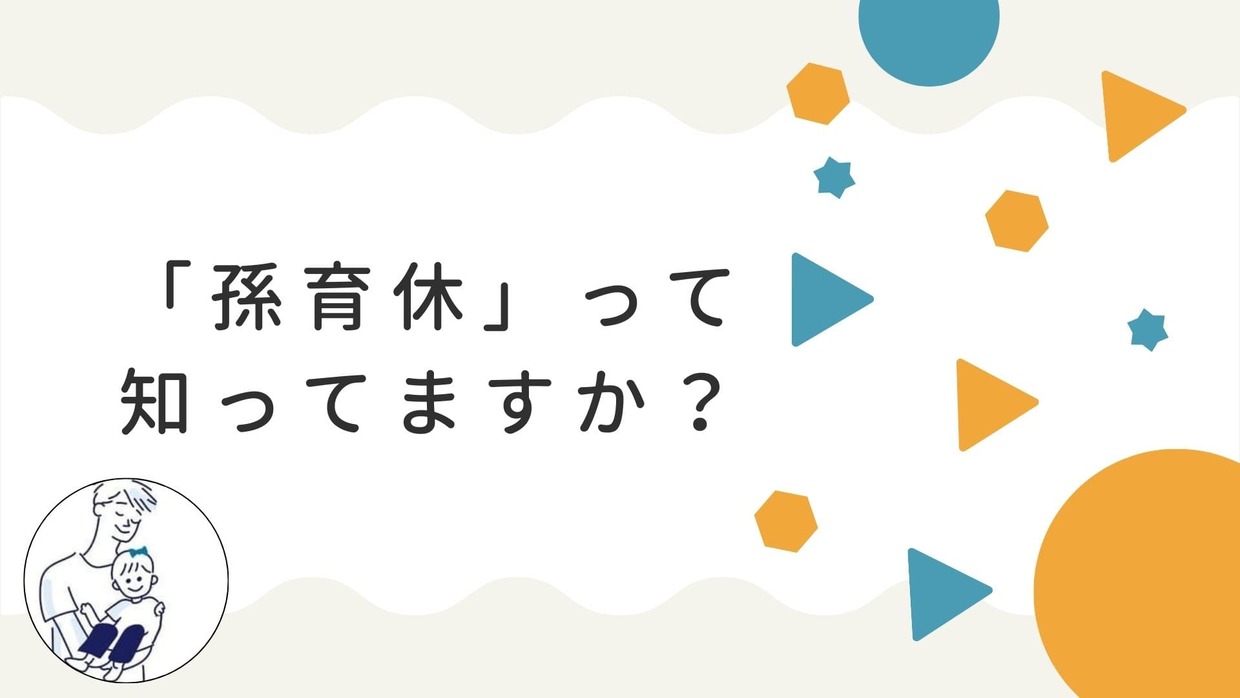どうも!「らんパパうーた」です。
6か月間の育児休業(育休)取得経験をもとにパパ、ママに役立つ情報発信しています!
コラムでは、育児休業などに関するニュースを「らんパパうーた」の考えや意見を交えてお届けします。
そもそも「孫育休」ってなに?

「孫育休」とは、祖父母が育児をサポートするために取得できる特別休暇のことです。
この制度は、宮城県が2023年1月に導入し、都道府県レベルでは全国初の取り組みとなりました。
宮城県の村井知事自身も、孫の育児を支援するために3日間の休暇を取得しています。
ちなみに、千葉県四街道市長が「育児を目的とした休暇」を約1か月間取得! と同じくの知事は特別職にあたるため、この制度の対象には含まれていません。
なぜ今、「孫育休」が必要なのか?

「孫のために祖父母が休暇を取る」。この制度に、驚きや違和感を覚える方もいるかもしれません。
「らんパパうーた」も「孫育休」に違和感を感じています。
ただ、この制度の背景には、社会の構造が大きく変わったことがあると思っています。
親の孤立
共働きが当たり前となり、子育て家庭は時間的、精神的に大きな負担を抱えています。
加えて、近くに頼れる親族がいない、地域のつながりが薄い中で、親たちは子育てをしています。
祖父母世代も働いている
祖父母の存在は子育ての心強い支えになり得ますが、祖父母世代は、定年退職後も働いている人が多く、「手伝いたくても手伝えない」状況にあります。
「孫育休」はギャップを埋めるための制度
「孫育休」は、助けたいけれど助けられないギャップを埋めるための制度だと考えています。
核家族化と会社員中心の社会

平成以前は、祖父母・親・子どもが同じ家に暮らす「三世代同居」が一般的で、子育ては、家族全体で行われてきました。
また、地域や親戚のつながりも密で、自然と子育ての手が集まる仕組みがありました。
核家族化により、親だけが子育てを担う
高度経済成長期以降、日本の家族構成は大きく変化し、都市への人口集中などにより核家族が進み、子育てを行うのが「親だけ」に絞られてきました。
サラリーマンが増え、家族の生活と仕事は切り離された
また、サラリーマンという働き方が広がり、家と職場が分離されるようになったことで、家族の生活と仕事は切り離されていきました。
祖父母の支援も簡単には届かない距離になった
その結果、育児の現場は物理的にも精神的にも孤立し、祖父母の支援も簡単には届かない距離になってしまいました。
「孫育休」は社会構造の変化に対する応急処置

「孫育休」は、単なる新しい福利厚生制度ではないと考えています。その背景には、核家族化・高齢化・共働きの進行があります。
親だけに子育てを任せるのは限界
親世代だけに育児を任せるには限界があります。しかし、昔のように三世代で暮らし、祖父母が自然と手を貸せるような環境はすでにありません。
「孫育休」は応急処置
「孫育休」は、断絶された関係を制度の力で一時的につなぎ直す仕組みだと考えることができます。
言い換えれば、「孫育休」は、社会構造の変化でこぼれ落ちた「子育ての担い手」を、つなぎ合わせるための応急処置なのです。
社会はどう子育てに向き合うべきか

「孫育休」のような制度だけで本質的な課題が解決するわけではありません。
誰が子育てを担うのか。子育てをどう支え合うのか。
これからの社会には、「誰が子育てを担うのか」「子育てをどう支え合うのか」という根本的な問い直しが求められます。
柔軟な働き方、地域ぐるみの子育て支援、多世代のつながりの構築が必要です。
社会全体で子育てに関与する覚悟が必要
企業や行政は「子育ては女性のもの」という前提を見直し、祖父母を含む多様な支援のあり方を制度として整えていく必要があります。
子育てはもはや家庭内だけで完結できる時代ではありません。社会全体で関与する覚悟が問われています。
まとめ:制度の裏にある「社会の変化」を見つめてみる

「孫育休」を通じて見えてくるのは、「家族のかたち」や「働き方」が大きく変わってきたということです。
制度が整うこと自体が進歩
昔はできていたことが、今は制度がないとできないのは一見寂しいようで、制度が整ってきたこと自体が、進歩でもあると思います。
なぜ必要とされるようになったのかを考える
大切なのは、制度の存在だけで安心するのではなく、「なぜ必要とされるようになったのか」を考え続けることです。
「孫育休」は子育てを見つめなおすきっかけ
「孫育休」をきっかけに、どんな社会で子育てをしているのか、改めて見つめ直すことが求められているのではないでしょうか。
以上、「らんパパうーた」でした。