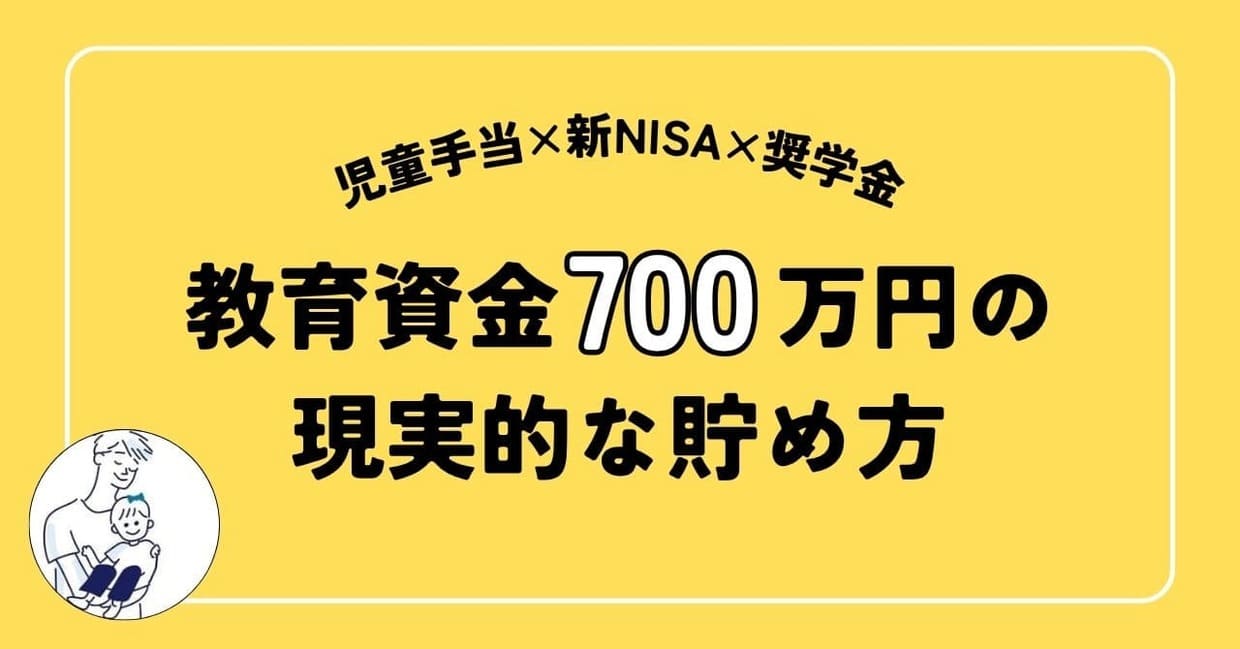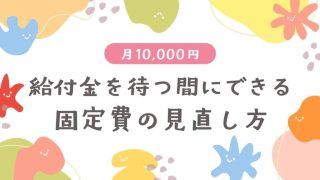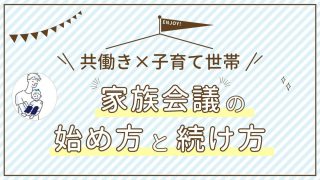最近、子どもが生まれたんだけどさ、子どもの教育はお金がかかるよね。
教育資金ってどうやって貯めればいいのかな?

まずはお子さんの誕生、おめでとう!
教育資金は、現金(児童手当)+投資(NISA)+奨学金を組み合わせて、時間をかけて準備するのがおすすめだよ。
ちなみに我が家では、一人あたり700万円を目標にしているよ!

なるほどね〜。
そのお金ってどうやって捻出してるの?

まずは児童手当を全額貯蓄に回してるよ。
18年間で大体200万円前後になるんだ。

児童手当だけでもそんなに貯まるんだね!
じゃあ、それ以外は?

あとは新NISAを活用して、オルカン(全世界株式)に毎月1.5万円ずつ積み立ててるよ。
もちろん投資だから元本割れのリスクもあるけど、18年間の長期投資ならそのリスクを抑えられるんだ。

なるほど。
でもやっぱり、投資って怖いイメージもあるなあ。

その気持ち、めちゃくちゃわかる!
でもね、長期・分散・積立で、元本割れの可能性はかなり低くなるよ。

へぇ〜、長期・分散・積立が大切なんだね。
でも、もし足りなかったらどうするの?

そこも一応考えてるよ!
老後資金用のNISAを一部活用したり、第3子の児童手当や奨学金制度を組み合わせて、不足分をカバーする予定だよ。
この記事では、教育資金の目標金額を700万円にした理由と教育資金の貯め方を紹介します。
- 教育資金の目標額を700万円にした理由
国公立大学一人暮らし・私立大学自宅通学に対応可能 - 児童手当を全額貯めて190〜215万円
- 新NISAで月1.5万円積み立てて300〜650万円
- 元本割れを想定して複数の状況をシミュレーションする
悲観シナリオ(元本割れ)で合計500万円
控えめシナリオ(利回り3%)で合計630万円
平均シナリオ(利回り7%)で合計850万円 - 教育資金が不足した時のBプラン
老後資金用のNISAから一部を取り崩す
第3子の児童手当で備える
奨学金で備える - 「子どもはどうしたいか」が大切
- 0歳と3歳のパパ
- 合計6か月間、育児休業を取得
- ランニングがライフワーク

教育資金の目標額を700万円にした理由
我が家では、教育資金の目標額を一人あたり700万円に設定しています。
これは、大学に進学したときの入学金・授業料・生活費を含めた金額です。
学費合計は約250万円〜約400万円
文部科学省の「国公私立大学の授業料等の推移」によると、大学4年間の学費はおおよそ次のとおりです。
| 4年間の学費(入学金含む) | |
| 国公立大学 | 約250万円 |
| 私立大学 | 約400万円 |
生活費合計は約200万円~約400万円
また、日本学生支援機構の「学生生活調査(令和4年度)」によると、大学に進学した際の生活費は次の通りです。
| 年間の生活費 | 4年間合計 | |
| 自宅外(一人暮らし) | 約100万円 | 約400万円 |
| 自宅通学 | 約50万円 | 約200万円 |
学費・生活費の合計は約600万円~約650万円
学費と生活費を合計すると、大学進学に必要な費用は以下のようになります。
| 学費+生活費(4年間) | |
| 国公立大学 + 一人暮らし | 約650万円 |
| 私立大学 + 自宅通学 | 約600万円 |
国公立大学一人暮らし・私立大学自宅通学に対応可能
こうしたデータを踏まえ、我が家では「国公立大学の一人暮らし」または「私立大学の自宅通学」 のどちらの進路にも対応できるよう、教育資金の目標額を一人あたり700万円 としました。
貯蓄で備える|児童手当を全額貯めて190〜215万円!
児童手当を全額貯めておくことで、教育資金の約3割をカバーできます。
児童手当は、次代を担う子供の健やかな成長に資することを目的として、国からすべての子育て世帯に支給される手当です。
生活費として使わず、そのまま貯蓄すれば、教育資金の土台を確実に作ることができます。
支給額は、0歳から3歳未満は月額1.5万円、3歳以上から18歳の年度末まで1万円です。
これを全額貯めると、合計で190万円~215万円になります。
つまり、児童手当を貯めておくだけで、教育資金の約3割が準備できるということになります。
2024年10月に児童手当が大幅拡充
2024年10月から、児童手当が大幅に拡充されました。
主な変更点は次の4つです。
- 所得制限が撤廃され、すべての子育て世帯が支給対象に
- 支給対象が高校生年代まで拡大
- 第3子以降の支給額が月3万円に増額
- 支給回数が年3回から年6回に変更
この変更によりすべての世帯で教育資金が貯めやすくなりました。
参考:政府広報オンライン「児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を」
投資で備える|新NISAで月1.5万円積み立てて300〜650万円!
我が家では新NISAを利用し、投資で教育資金を準備しています。
教育資金が必要になるのは18年以上先です。
現金は短期的には価値を安定して保つのに向いていますが、長期になるとインフレによって価値が目減りする可能性があります。
そのため、教育資金は現金と投資で備えています。
現在、一人あたり毎月1.5万円を新NISAで積み立てています。
18年間運用した場合の想定額は次のとおりです。
- 元本:324万円
- 控えめな利回り3% → 約430万円
- 平均的な利回り7% → 約650万円
もちろん、投資にはリスクがあります。
相場次第では、324万円を下回り元本割れする可能性もありますが、18年以上の長期投資では元本割れのリスクが緩やかになる傾向があります。
教育資金を投資で準備することが、インフレ対策になります。
新NISAは「非課税枠」と「非課税期間」が大幅拡充
2024年からスタートした新NISAによって、教育資金をより準備しやすくなりました。
いわゆる旧NISAでは「非課税期間が最長5年」「年間120万円まで」という制限がありましたが、新NISAでは次のように改善されました。
- 非課税期間:無期限
- 非課税限度額:1,800万円
これにより、「子どもの教育資金」だけでなく、「老後資金」も準備できるようになりました。
参考:金融庁「NISAを知る」
元本割れを想定して複数の状況をシミュレーションする
投資にはリスクがあります。
教育資金が必要になった18年後のタイミングで、株価が一時的に下がっている可能性もあります。
そのため、我が家では、3つのシナリオ(悲観・控えめ・平均)を想定して教育資金をシミュレーションしています。
| – | 現金 (児童手当) | 投資 (NISA) | 合計 |
| 悲観シナリオ (元本割れ) | 200万円 | 300万円 | 500万円 |
| 控えめシナリオ (利回り3%) | 200万円 | 430万円 | 630万円 |
| 平均シナリオ (利回り7%) | 200万円 | 650万円 | 850万円 |
悲観シナリオ(元本割れ)
現金と投資の合計は500万円です。
目標の700万円に約200万円足りない計算です。
株式市場の下落局面では元本割れのリスクがあるので、そのようなケースも想定しておくことで、実際に下落しても淡々と投資を続けられます。
控えめシナリオ(利回り3%)
現金と投資の合計は630万円です。
目標の700万円には届かないものの、ほぼ近い水準までカバーできます。
この利回りであれば、オルカンを長期で積み立てた場合の再現性も比較的高いといえます。堅実に備えたい人はこのシナリオを基準にするといいと思います。
平均シナリオ(利回り7%)
現金と投資の合計は850万円です。
目標金額を150万円上回る結果です。
歴史的に見れば、全世界株式インデックスの平均リターンは年5〜7%ほどです。そのため、現実的に十分狙える結果といえます。
教育資金が不足した時のBプラン
悲観・控えめシナリオでは、教育資金が目標金額に届かないことがわかりました。
そのため、「もしも」に備えたBプランを用意しています。
- 老後資金用のNISAから取り崩し
- 第3子の児童手当(18歳まで月3万円)
- 奨学金制度の活用(授業料免除・無利子型を想定)
貯蓄や制度を組み合わせることで、元本割れが起きても柔軟に対応できると考えています。
あらかじめ複数のシナリオとBプランを用意しておけば、株式市場の上下を気にせず、教育資金を淡々と積み立てることができます。
老後資金で備える|長期投資で2,000万円超
「らんパパうーた」は、老後資金のためにNISAで運用しているS&P500を、教育資金のセーフティネットとしています。
教育資金が必要になるのは15年以上先ですが、老後資金の運用期間はさらに長く、時間を味方にできます。
決まった額を毎月積み立てれば、一部を教育費に回しても老後への影響は小さいと考えています。
現在の積立額は毎月33,333円です。年間で約40万円。30年以上の長期運用を想定しています。
このまま継続した場合、約2,500万円から約5,200万円になっている想定です。
この資産の一部を取り崩し、教育資金に充てる計画です。
「老後資金を取り崩して大丈夫なの?」と感じた方もいるかもしれません。
65歳以降も自分のペースで働き続けるつもりであり、加えてiDeCoも少額ながら積み立てています。
そのため、老後資金を教育費に回しても老後の生活に支障はない見込みです。
老後資金を教育資金のセーフティネットにしたとしても、長期で運用すれば、老後への影響は最小限にできます。
第3子の児童手当で備える|全額貯めると648万円
2024年10月に児童手当が拡充され、第3子以降は月額3万円支給されるようになりました。
所得制限も撤廃されたため、すべての子育て世帯が対象になります。
第3子は第一子が22歳の年度末を迎えるまで月額3万円受給可能
ただし、「第3子」の数え方に注意が必要です。
第一子が22歳の年度末を迎えると、第3子が「第2子」として扱われてしまいます。
そのため、第一子が22歳の年度末を迎える前に第3子が18歳の年度末を迎えられれば、第3子は児童手当を最大限受給できます。
3人分の児童手当で目標金額の47%を賄える
3人分の児童手当をすべて貯めると、合計で約1,000万円です。
教育資金の目標金額を一人あたり700万円(合計2,100万円)としても、児童手当だけで約47%を賄える計算です。
児童手当は教育資金の軸になる
投資で元本割れが起きて教育資金が不足しても、第3子の児童手当を活用すれば十分カバーできる可能性があります。
つまり、「児童手当を全額貯める」ことは、教育資金計画を安定させる強力な戦略になります。
奨学金で備える|最大306万円の支援が受けられる
2025年(令和7年度)から、子どもが3人以上いる世帯を対象に、大学などの授業料無償化制度が拡充されました。
対象となる世帯は、授業料の支援が毎年受けられるほか、入学金も免除されます。
支援額の目安は以下の通りです。
授業料:年間 最大70万円 × 4年間 = 280万円
入学金:26万円
合計:最大306万円
また、この制度には所得制限がない点も大きな特徴です。
多子世帯であれば、一定の条件を満たすことで誰でも対象になります。
対象になるための条件に注意
児童手当と同様に、「3人以上の子どもを同時に扶養していること」が条件です。
そのため、上の子が就職や独立などで扶養から外れると、「3人目扱い」から外れて支援対象外になる可能性があります。
教育費の計画を立てる際は、子どもたちの進学・就職のタイミングも踏まえて、支援が途切れないように意識しておくことが大切です。
参照:文部科学省「多子世帯の大学等の授業料等無償化について」
我が家の教育資金プランまとめ
我が家では、一人あたりの教育資金の目標額を700万円に設定しています。
まず、児童手当を全額貯蓄し、18年かけて現金を約190万〜215万円貯めます。
次に、新NISAを使って毎月1.5万円をオルカンに長期投資します。
元本324万円を18年間運用した場合、以下のような結果を想定しています。
- 元本割れ(悲観シナリオ):約300万円
- 利回り3%(控えめシナリオ):約430万円
- 利回り7%(平均シナリオ):約650万円
この時点で合計は約490万円〜865万円となり、教育資金の目標700万円を達成できる可能性もあります。
ただし、未達となる場合も考慮して、プランBを用意しています。
プランB|教育資金を支える3つのバックアップ
- 老後資金の一部(2000万円〜)を活用
- 第3子の児童手当(満額で648万円)を全額貯蓄
- 奨学金制度を活用し、最大306万円の支援を受ける
これらを組み合わせることで、一人あたり700万円の教育資金を無理なく確保できる見通しです。
制度は活用しつつ、自分たちでも備える
少子化が進む中で、児童手当や奨学金などの支援制度が廃止される可能性は低いと考えています。
とはいえ、制度頼みにするのではなく、制度を活用しながら自分たちで教育資金を準備する姿勢が大切だと考えています。
大切なのは「子どもがどうしたいか」
教育資金の最終的な使い道は、子どもの希望次第で変わります。
生まれた時点では将来の進路はわかりません。ですが、進学したいとなったときに大きいお金を用意することも難しいです。だからこそ、早めに貯蓄や投資を始めておく必要があります。
そして何より大切なことは、日々の会話や家族会議を通じて、子どもの希望を尊重し、将来を一緒に考える姿勢だと考えています。
子どもが就職を選んだときでも、準備していた教育資金は「人生の使い時」を支えるお金になると思います。
「子どもが人生をどう歩みたいのか」それを支えるための資金が「教育資金」なのかなと思いました。
以上、「らんパパうーた」でした。